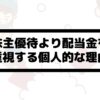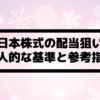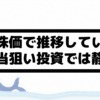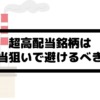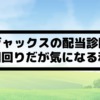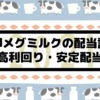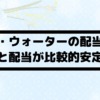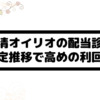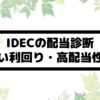配当金狙いの株式投資。過去の失敗経験、痛い経験について
今回、私が配当金を狙って株式投資をした際の失敗談、実際にあった痛い経験を書いていきます。
特に株式投資を始めたばかりの頃は、配当利回りの高さにつられて痛い思いを何度もしました。現在はその経験から失敗が減ってきましたが、肝に銘じています!
業績悪化で減配当、株価下落で最後は無配当に
まずは配当金狙いとして最悪な無配当に転落した経験です。
配当狙いの場合、当然ですが高利回りが良いですよね。しかし、利回りが高いパターンは複数あります。
オススメ銘柄、推奨銘柄の罠
下記は大塚家具の過去の株価チャートです。

参照:SBI証券 大塚家具株価チャートより
2015年12月期、2016年12月期の年間配当金は80円でした。株価2,000円で取得しても配当利回りが4%、1,500円以下で取得した場合は5%を越えました。
有名な投資家や雑誌などで「大塚家具は年間利回りが5%を超えているのでおいしい!」と紹介されていましたが、次第に業績悪化。
減配から無配へ、そして上場廃止に
大塚家具は2017年12月期の配当が半分の40円に、2018年12月期からは無配当となりました。
当然、株価も大きく下落。最終的にはヤマダホールディングス(ヤマダ電機)に吸収される形で2021年8月末に上場廃止となりました。
現状だけで判断するのは危険
大塚家具は利益以上の配当金を出すこともありました。つまり、かなり業績が良くならないと配当を維持するのはそもそも無理でした。
現在の利回りだけをみて判断するのではなく、なぜ高い配当利回りなのか。配当金が減りそうな雰囲気をつかむことが重要という経験でした。
株価が下落して高配当は危険信号
配当利回りの算出方法は単純で「配当金額」と「株価」のみで決まります。
配当利回りが高いというのは「配当金が増えた」か「株価が下落した」の二つです。相場全体が下落しているわけでもないのに利回りが高い。というのは何かしら問題があることが多いですよね。
「なぜ高配当なのか」、「なぜ高配当になったのか」冷静に考えることが大事ですね。
安定配当で適正水準も安心できない
配当推移が安定、配当性向も問題ない銘柄は安全かというと、絶対安全とは言えないですよね。
安定銘柄の代表格が無配になり、株価暴落
下記は東京電力の株価チャート20年分です。

参照:SBI証券 東京電力ホールディングス株価チャートより
2000年頃から年間配当60円前後で安定していました。
高配当とはいえないですが、買った時期によっては悪くない利回りでした。多くの人が業種的にも「安定している」と考え、銀行や証券会社から薦められ保有する人も多かったです。リーマンショック時にも影響が比較的小さく、安定配当を継続していました。
不測の事態発生
しかし、東日本大震災以降に株価は暴落、2012年3月期から無配当が続いています。今後も配当金が戻るにはかなりの時間がかかる可能性があります。震災前にこの事態を想定できた人はほぼいないです。
「業績が安定、利回りが平均的ならばリスクは低め」というのを目にする事がありますが・・・
安全・安心と言われている銘柄でも100%安全なものはないという経験でした。
失敗経験から分かる事とは
株式投資に限らないですが「投資に絶対儲かる、絶対安全」は無いですね。長く株式投資をしていると必ず暴落に当たります。いつ、何が起きるか分からないのが投資です。
本当の分散とは
「絶対に安心できるのは無い」と言う意味でも分散は必要だと思います。しかし、分散してもほとんどの株が下落することもあります。そのため、現金比率(不測の事態に備えて現金を残す)や株式以外の選択肢を取ることが本当の分散なのかもしれません。
疑問を持つこと
雑誌などで紹介されことの多い高配当銘柄ですが、基本的には現時点での利回りです。しかし、重要なのは「どうして高い利回りなのか」ですよね。
紹介された銘柄、高配当銘柄のすべて悪いというわけではないですが、紹介された銘柄が大きく減配・無配となるケースを私はたくさん見てきました。「なぜ?」という疑問を持つことが重要と考えています。
注:長期保有の配当金狙い投資としてのあくまでも個人的な感想です。投資の判断はくれぐれも個人の判断でお願いします